 歴注・選日・吉日のお話
歴注・選日・吉日のお話 甲子日(きのえねひ)ってどんな日?長く続けたい物事を始めるならこの日!ですよ♡暦注(れきちゅう)の選日編⑨
60日に一度やってくる甲子日。「物事を始めるのにピッタリ」の日。甲子園球場の名のように甲子の年、甲子の日は縁起が良いとされました。ご自分の運気+良い運気を取り入れることによって、今まで躊躇してできなかったことを始めてみましょう。『甲子夜話(かっしやわ)』という江戸時代に書かれた随筆集はなんと20年続いたんですよ。
 歴注・選日・吉日のお話
歴注・選日・吉日のお話 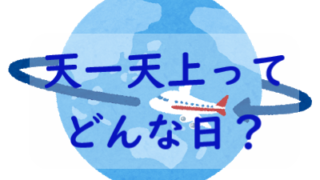 歴注・選日・吉日のお話
歴注・選日・吉日のお話 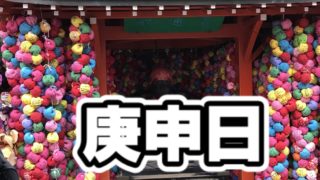 歴注・選日・吉日のお話
歴注・選日・吉日のお話 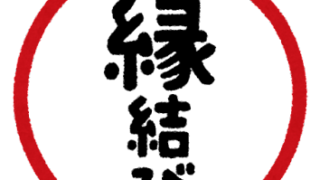 コラム
コラム 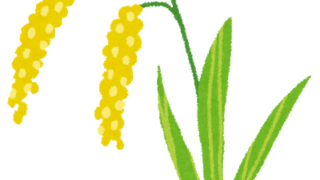 歴注・選日・吉日のお話
歴注・選日・吉日のお話 一粒万倍日って新しく始めるには最高のラッキーデーなんですよ。仕事始め、開店、種まき、お金を出すことが全部吉。良い事も悪い事も万倍になる一粒万倍日。ぜひしてほしい事をお教えします。
 歴注・選日・吉日カレンダー
歴注・選日・吉日カレンダー  二十四節気のお話
二十四節気のお話  歴注・選日・吉日のお話
歴注・選日・吉日のお話  歴注・選日・吉日のお話
歴注・選日・吉日のお話